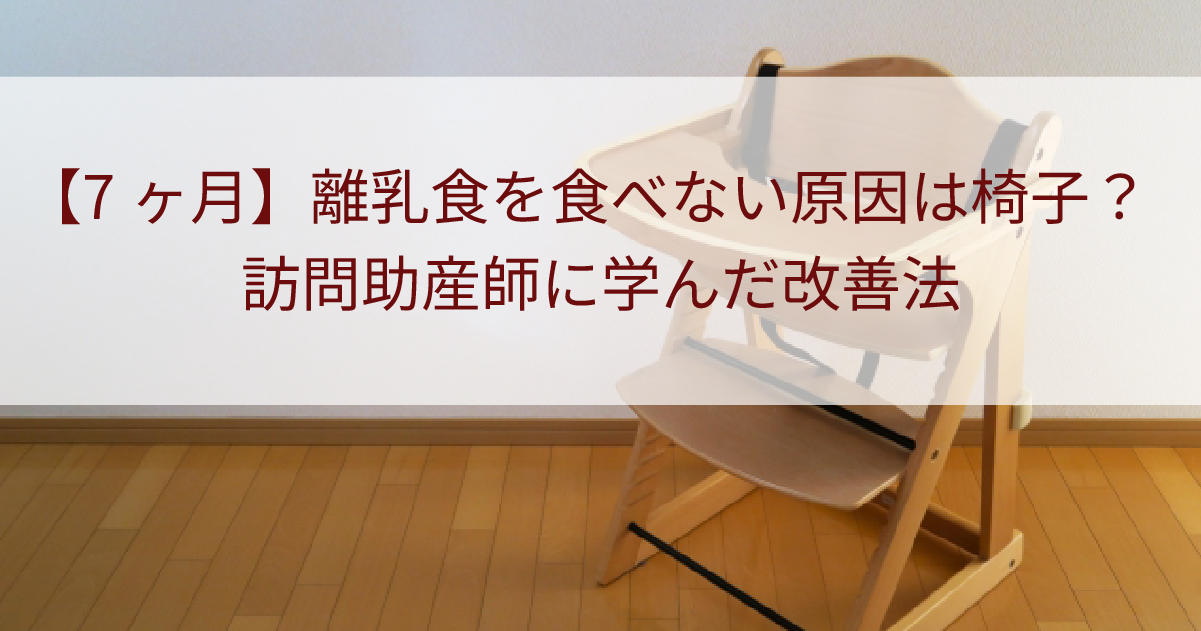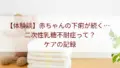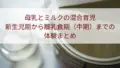はじめに
「せっかく作った離乳食を、全然食べてくれない…」そんな悩みを抱えていませんか?
私も生後7ヶ月の息子が、スプーンを口に近づけても顔をそむけたり、遊び始めたりして困っていました。
用意したものを食べてもらえず、混合育児も思うようにいかず、精神的につらく感じる日がありました。
そこで、訪問助産師さんに相談したところ、原因は“食べる姿勢”と“椅子の使い方”にあるかもしれないと気づくことができました。
この記事では、7ヶ月の赤ちゃんが離乳食を食べない原因と、椅子を見直して改善できた体験談をまとめました。
同じ悩みを持つママ・パパのヒントになれば嬉しいです。
利用したプラン(概要)
今回利用したのは、訪問型の2時間コースです。事前にスリッパやお茶を用意していましたが、話が弾んでしまい出すのを忘れるほどリラックスしてお話できました。
実際の相談内容と気づき
助産師さんは私の悩みをじっくり聞いてくれ、励ましの言葉で気持ちを切り替えられました。特に印象的だった指摘は「腰がまだ座っていないのに椅子を用意していない」という点。書籍で離乳食については学んでいたつもりでしたが、椅子の“用意タイミング”がずれていたことに気づかされました。
相談で得た具体的なポイント
- 姿勢(体幹の安定)が食べやすさに直結する
- 環境面(床材・テーブル・スプーンサイズ)も要チェック
- すぐに結果を求めず「気分」も尊重する
椅子(ハイチェア)選びのポイント
助産師さんに教わった、椅子選びのチェックリストです。
- 調整できる足置き板:高さだけでなく位置も変えられるもの
- 座面の前後調整:深さを調整できると安定する
- 背もたれ:肩より上まで支えるものが望ましい
- 膝が90度になること:足裏がしっかりつく高さが理想
- 机とお腹の距離:こぶし1つ分(拳1つ分の隙間)
避けたほうが良い点・注意点
- タオルでの高さごまかしは限界がある(長期的にはハイチェアがおすすめ)
- 脚の形や体格によって合わない製品がある(例:Banbo は脚が太めの子は合わないことあり)
- 購入は「実際に座らせてみて」からが安心
その他、助産師さんからの実用アドバイス
床材について
カーペットは見た目は安心ですが、食べこぼしの掃除でストレスになりがち。拭き取りやすい素材にすると家事負担が減ります。
テーブル(ローテーブル vs ダイニング)
ローテーブルは子どもが触りやすく、落としたり登ったりしやすい点がデメリット。可能ならダイニングテーブルを使うか、食事スペースを工夫しましょう。(我が家は寒さ対策でこたつを使っているため工夫が必要でした)
スプーンのサイズ
生後4〜5ヶ月で使っていた小さなスプーンはすぐサイズアウトします。口の大きさに合うスプーンを選ぶことが重要です。
おまけ 少食さんの卵アレルギー対策のひと工夫
卵のステップアップが難しい場合、そぼろを作って冷凍しておくと便利です。卵白だけの冷凍は解凍が難しいため、全卵や他食材と混ぜて冷凍する方法がおすすめです。(※実践したら追ってレビュー予定)
まとめ まず見直すべきは「環境」と「姿勢」
- 「食べない=離乳食のせい」と結論づける前に、椅子や姿勢・食器など環境面をチェックする
- 腰が座る前でも、バスタオルなどで脇を安定させる工夫をしてみる
- スプーンや食器は成長に合わせて見直す
- 気分の波はあるので、食べなければ「今日は気分じゃない」と割り切ることも大事
- 目標量と比べ、今日80%でも、明日120%食べるならそれでいい、目標は毎日60%で
- 体重は大体でいいので把握しておき、困ったら悩まず相談をする
感想
訪問助産師さんに話を聞いてもらえたことで、気持ちが楽になり、具体的な改善策も得られました。漠然とした不安が整理され、「次にやること」が明確になったのが大きな収穫です。
今後の予定
卵白の冷凍など、実際に試したら追記でレポートします。